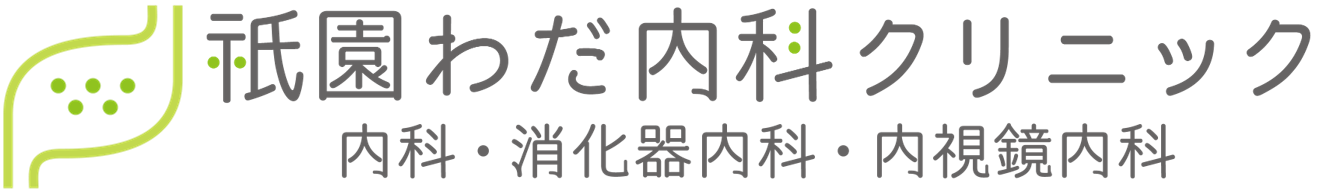ID管理・入力の不要な『LINE予約』をお勧め。
LINEは本人様のみの登録となります。
複数名のご予約はWEB予約よりお願いします。
(同一メールアドレスで複数名の登録が可能です)

胃痛や胃もたれは
胃炎の可能性があります
胃炎とは

胃には胃酸が分泌されています。
口から入ってきた飲食物の消化と細菌や微生物の殺菌という重要な役割を担っています。
胃の粘膜が胃酸にさらされても溶かされないのは、粘液がバリアとして粘膜を守り、胃酸が直接胃粘膜に触れないようにしているからです。
ピロリ菌は胃粘膜のつながりを破壊し、炎症や潰瘍を引き起こすことが知られています。
また、消化機能は自律神経によってコントロールされているため、不安やストレスなどが重なることで防御機能がうまく働かなくなることがあり、こうした原因の影響で胃に炎症や痛みを起こすことがあります。
胃炎の症状

急性胃炎
胃やみぞおち付近の、痛み・膨満感・不快感・むかつき・嘔吐などの症状を急激に起こします。
大きく傷付いた場合は、吐血や下血を起こすこともあります。
慢性胃炎
胸焼け、むかつき、胃もたれ、食欲不振などが起こり、空腹時や食後など決まったタイミングで症状を起こすケースもあります。
ただし、慢性的な胃粘膜の炎症があってもほとんど症状を起こさずに進行することもあります。
胃炎の原因
急性胃炎の原因

暴飲暴食、アルコールの過剰摂取、薬の副作用で起こることが多くなっています。
暴飲暴食やアルコールによるものは胸やけや、胃もたれを伴うことが多いです。
食中毒菌による急性胃炎は急な胃痛が特徴です。
アニサキスによる胃痛は激しい胃痛がおこります。前の食事でサバ・アジなどの摂取があります。
慢性胃炎の原因
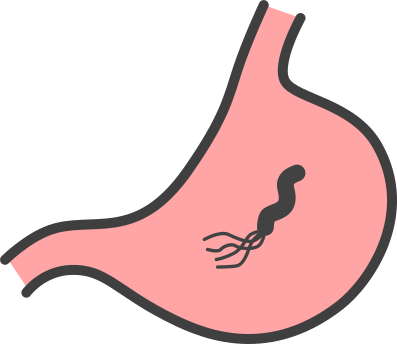
ピロリ菌感染によるものがほとんどを占めています。
衛生状態が改善した日本では感染者が減少傾向にあるとはいえ、先進国としては例外的に今も感染率が高い状態が続いています。
除菌治療でピロリ菌を除去することは、炎症や潰瘍の再発を防ぐためにも重要ですし、次世代の感染を防ぐためにも効果的です。
胃炎の診断
胃炎の治療
内服治療とピロリ菌除菌治療

生活習慣の改善

胃酸分泌が過剰になると炎症リスクが上がるため、胃酸分泌を促す飲食物をできるだけ避けましょう。
暴飲暴食やアルコールの過剰摂取をしないようにして、ブラックコーヒー、唐辛子など刺激の強い香辛料、油っぽい食事を控えます。
ストレスなどの影響を大きく受けて発症しやすい場合には、規則正しい生活、十分な睡眠や休息、そして上手なストレスの解消なども重要です。